【スパイスは体にいいの?悪いの?】効果・副作用・体質別の使い方をわかりやすく解説!
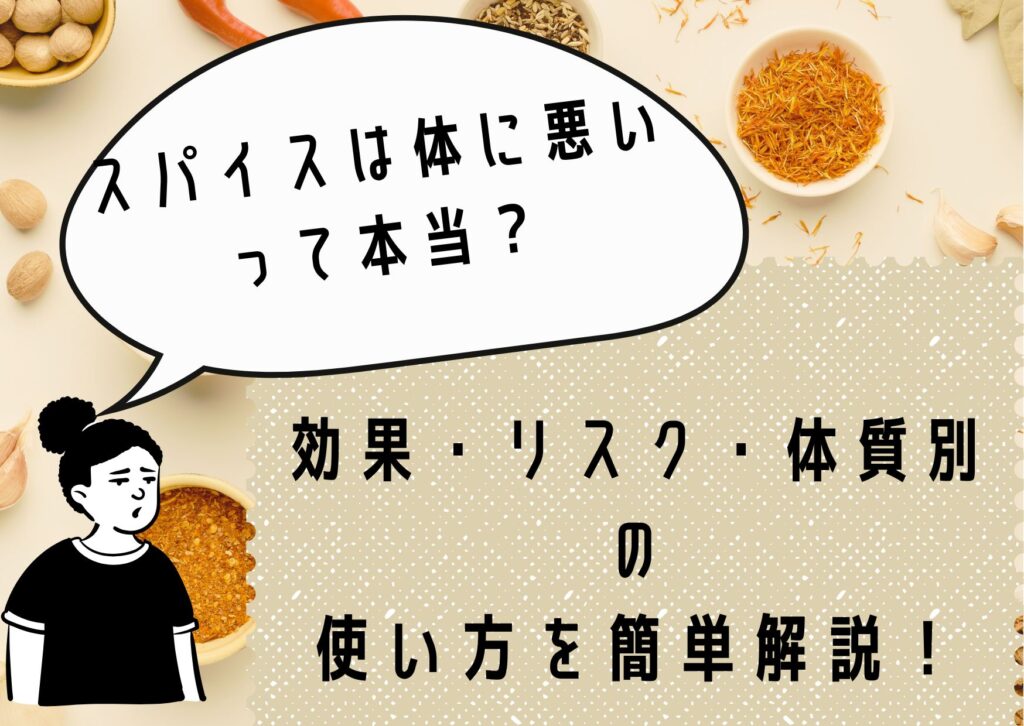
こんにちは!ウタコです。
ブログに来ていただきありがとうございます。
はじめに|「スパイス=体に悪い」は思い込みかも?
最近、「スパイス料理」や「チャイ」が流行ってますよねー!
おしゃれカフェでも、チャイやスパイスカレーやスパイスを使ったおやつもたくさんあったり!
私も大好きです!
でも一方で、「スパイスって刺激が強そう」「胃が荒れそう」なんて、不安に感じたことはありませんか?
私も以前、なんとなく「体に悪そう」「何か副作用があるのでは?」と避けていた時期がありました。
でも調べてみると、スパイスには美容や健康に嬉しい働きがたくさんあることがわかったんです。
この記事では、スパイスの効果や気を付ける点、体質に合ったスパイスの選び方や楽しみ方をご紹介します。
少しでも参考になれば幸いです。

昔から体が弱く年齢を重ねるにつれて、より様々な不調を感じるように。
自身で何とか体調を改善できないか?と、東洋医学やスパイス・ハーブなどを勉強。
セルフメディケーションカウンセラーの資格とスパイス&ハーブ検定資格を保有。
スパイスは本当に体に悪いの?|実は薬膳にも使われる“自然のパワー”

まず前提として、スパイスそのものが「体に悪い」という科学的根拠はありません。
むしろ、漢方や薬膳の世界では、スパイスは昔から“食薬(しょくやく)”として活用されてきた存在で、色々な効果が期待できます。
スパイスの代表的な健康効果
・冷え性の改善:シナモンやジンジャーは、体を内側からポカポカに
・消化をサポート:クミンやフェンネルは、胃腸の調子を整えてくれる
・代謝アップ:ターメリックや唐辛子は、脂肪燃焼を助けてダイエットにも◎
・抗酸化作用:クローブやカルダモンは、肌の老化予防やアンチエイジングにもおすすめ
一例でいくつかあげましたが、その他のスパイスにもそれぞれ効果があるので、
そのときの体調などに合わせて組み合わせるのがおすすめです!
とはいえ要注意!スパイスが体に悪いと言われる理由とは?
スパイスが「体に悪い」と言われる背景には、以下のような理由があります。
・刺激が強く感じることがある
特に唐辛子やブラックペッパーなどの辛味スパイスは、胃腸の弱い人には刺激が強すぎることも。

・摂りすぎは逆効果になることも
体に良いものでも、過剰に摂取すると胃もたれやのぼせの原因になることがあります。
・体質に合わないことがある
体が“熱”を持ちやすい人にとっては、熱性のスパイスが逆効果になる場合も。
・加工食品に含まれるスパイスは別物
スナック菓子やインスタント食品に使われているスパイス風味には、添加物も多く「体に悪そう」と思われがち。
✅持病がある人は、薬との相互作用が出ることもあるので医師に相談を!
✅妊娠中や授乳中は、使用を避けたほうがいいスパイスもあるので注意!
たしかに、スパイスは使いすぎたり、体質に合わなかったりすると、不調の原因になることもあります。
でも、それは「使い方の問題」。
自分の体調や体質に合ったものを、適量取り入れることが大切になってきます。
スパイスとの上手な付き合い方
初心者の方は、まず「無理せず、シンプルに」が付き合ってみるのがおすすめです。
この章ではスパイスを使う4つのコツをご紹介します!
①少量から試してみる
いきなり本格的なスパイス料理を作るのはハードルが高いので、スープや紅茶、ヨーグルトなどにささっとふりかけてみるところから始めてみると挑戦しやすいです。
→簡単な取り入れ方についてはこちらの章も参照してみてください。

②食材との組み合わせを考える
たとえば、冷えが気になるときはスープにジンジャーを。
熱っぽい時期には、爽やかなミントとフルーツを合わせてスムージーにするのも◎。
③加工食品ではなく“素材”から取り入れる
今はスナック菓子などの加工品にもスパイスが含まれていることも多いですが、そういったスパイスではなく、ホールスパイスやパウダーを使った料理の方が、体にやさしいので続けるのにはおすすめです。
④今の自分の体質を知っておく
自分の“今の体の状態”を知ることで、よりスパイスの力を生かすことができます。
次の章で簡単に体質をチェックできるリストを作成してみましたので、ぜひ確認してみてください。
【簡単診断】5分でできる!東洋医学ベースの体質チェック
東洋医学・薬膳では、体質に合わせて食材やスパイスを選ぶことが大切と言われています。
「スパイスが体に合わないかも…?」と不安な方は、まずは自分の体質をチェックしてみましょう!
A:気虚タイプ(エネルギー不足タイプ)
✅朝起きるのがつらい
✅少しの運動で疲れやすい
✅声が小さくて通らないと言われる
✅食後に眠くなりやすい
✅風邪をひきやすい
→ Aにチェックが多い人は「エネルギー不足タイプ」。
気虚タイプの人は、生命エネルギー(=気)が不足しがちで、全身に元気が回っていない状態です。
疲れやすく、免疫力や消化力も低下しやすい傾向にあります。
◆気虚タイプにおすすめのスパイス
エネルギーが足りていないので、まずは米やイモ・豆類などエネルギーを補い、
さらにエネルギーの巡りと胃腸をサポートしてくれる以下のようなスパイスがおすすめです。
・コリアンダー
・シナモン
気虚タイプは刺激のあるスパイスは汗をかいて体力を消耗するので摂り過ぎはNGです。
👇気虚タイプの方へはこちらの記事もおすすめ👇
【チェックリストあり】気虚とは?疲れやすい・やる気が出ない…気虚の原因&改善方法7選
B:血虚タイプ(血が足りないタイプ)
✅顔色が青白い
✅髪がパサつく・抜けやすい
✅目がかすむ・乾く
✅眠りが浅く、夢をよく見る
✅爪が割れやすい
→ Bにチェックが多い人は「栄養不足タイプ」。
血虚タイプは、体の中の「血(けつ)」が不足している状態。
血は栄養とうるおいを全身に届ける役割があるため、これが足りないと、肌・髪・爪などの不調や、不眠・情緒不安定が出やすくなります。
◆血虚タイプにおすすめのスパイス
そもそも栄養が足りていないので、鉄分を含む食材や黒い食材(黒ごま・黒きくらげなど)を摂りつつ、
気を巡らせる以下のようなスパイスを取り入れるのがおすすめです!
・シナモン
・クミン
👇血虚タイプの方へはこちらの記事もおすすめです👇
【チェックリストあり】血虚とは?疲れやすい、顔色が悪い…血虚の原因&改善方法7選
C:水滞タイプ(むくみ・だるさタイプ)
✅朝、まぶたや顔がむくみやすい
✅体が重だるくてスッキリしない
✅雨の日や湿気が多い日に体調が悪くなる
✅お腹に水がたまったような感じがある
✅頭が重く、めまいや吐き気が出やすい
→ Cにチェックが多い人は「むくみタイプ」
水滞タイプの人は、に余分な水分が溜まりやすく、巡りが悪くなっています。
特に消化機能(脾・胃)が弱りやすく、水分代謝もうまくいっていない傾向にあります。
そのため、食べすぎや冷たいものの摂りすぎには注意が必要です。
◆水滞タイプにおすすめのスパイス
余分な「水」を巡らせ、体を内側からスッキリ整えるスパイスを選ぶのがポイントです。
・ターメリック
・マスタード
・ブラックペッパー
むくみや重だるさに悩む水滞タイプの人には、「温める」「巡らせる」スパイスを取り入れるのがおすすめです。
👇水滞タイプの方へはこちらの記事もおすすめです👇
【チェックリスト付き】水滞(すいたい)とは?体が重だるい・むくみが気になる|水滞の原因と改善方法7選
D:気滞タイプ(ストレスタイプ)
✅イライラしやすく、気分の浮き沈みがある
✅ため息がよく出る
✅胸やお腹が張る感じがある
✅生理前になると不調が出やすい
✅便秘と下痢を繰り返すことがある
→ Dにチェックが多い人は「ストレスタイプ」。
気滞タイプは、ストレスや緊張により気の巡りが滞ってしまっている状態です。
これにより精神的にも肉体的にもモヤモヤしやすくなります。
特に女性は、生理前に強く出やすい傾向があるとされています。
◆気滞タイプにおすすめのスパイス
気の巡りを促し、リラックス効果のあるスパイスを選びましょう。
・シナモン
・クミン
・コリアンダー
・ターメリック
👇気滞タイプの方へはこちらの記事もおすすめです👇
【チェックリストあり】気滞とは?イライラやストレスで不調に…気滞の原因&改善方法7選
おすすめのスパイスの取り入れ方
いざ取り入れようと思っても買ったはいいけど、「どう使えばいいの?」「難しそう…」と感じて、
余らせてしまっている方も多いのでは?
毎日の生活の中で意外と手軽にスパイスは取り入れられるので、コショウを振りかけるような感覚で使ってみてください。
・朝の白湯にジンジャーをプラス:代謝アップ&温活に◎
・おやつタイムにシナモントースト:香りでリラックス効果も
・野菜炒めクミンをプラス:マンネリになりがちな定番メニューも一味違う味に
・市販のレトルトカレーにクミンを足してみる:香りと消化力アップ!
・スパイス入りチャイにする:ミルクティーにシナモンやカルダモンなど好きなスパイスと一振り
・無印良品などレトルトのスパイスカレーを活用:スパイス初心者にも安心の味
おわりに|スパイスは“正しく使えば”良い味方に
スパイスは決して「体に悪い」ものではなく、使い方次第で心と体のバランスを整えてくれる頼もしい味方です。
スパイスは、気虚や血虚などエネルギーが不足してるタイプの方より、水滞や気滞など体内の巡りが悪い方に特におすすめ◎
気虚や血虚の方はエネルギーや血を補う食材と合わせて取り入れるのがおすすめです。
このように、体質によっては合わないものもあるので、まずは自分の体としっかり向き合うことが大切。
ぜひ自分に合ったスパイスの使い方を見つけてみてください!
少しでもみなさまの気になることが解決できていたら嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
👇この記事を読んだ方におすすめの記事👇
【スパイス&ハーブ検定資格保有者が厳選】カレー以外でもつかえる!おすすめのスパイス5選
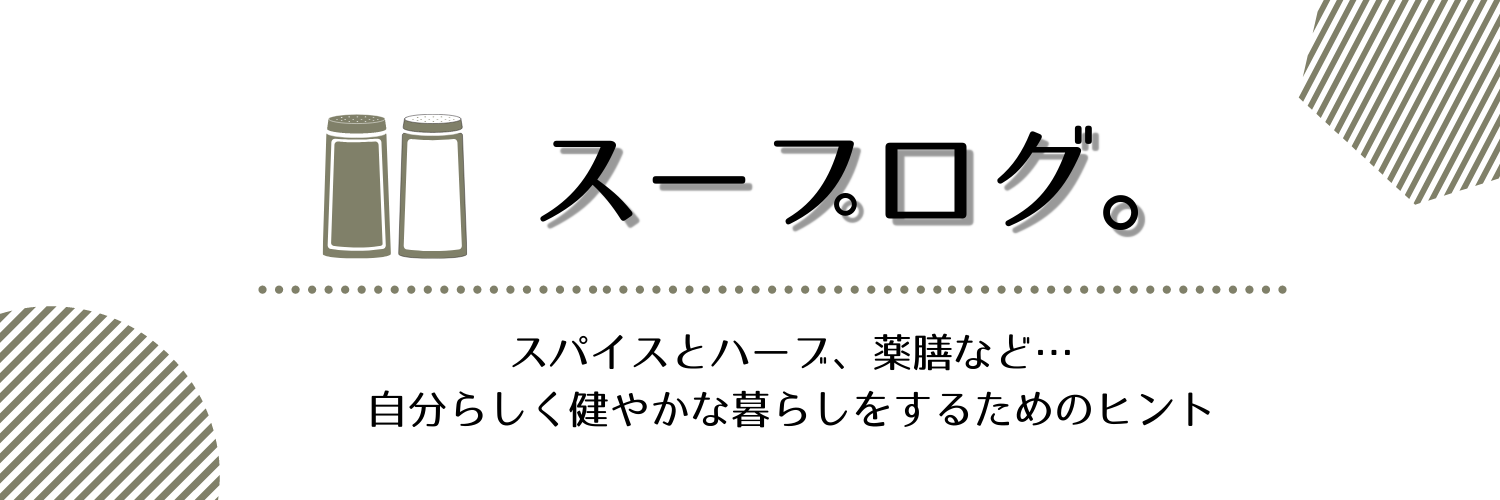

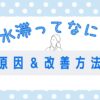
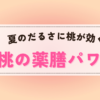

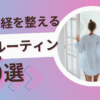
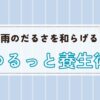
最近のコメント