梅雨の不調に「とうもろこし」が効く!むくみ・重だるさ対策におすすめ

こんにちは!ウタコです。
ブログに来ていただきありがとうございます。
梅雨の時期、なんだか体が重くてやる気が出ない…そんな不調を感じていませんか?
実はその不調、「湿気」による“水のめぐり”の乱れが原因かもしれません。
そんなときにおすすめなのが、身近な食材「とうもろこし」。
実はとうもろこしには、体内の余分な水分を排出してくれる力があり、東洋医学でも“梅雨にぴったりの養生食材”として知られています。
この記事では、とうもろこしの効果や手軽な取り入れ方、冷凍や缶詰を使った簡単レシピ、さらにはとうもろこし茶の魅力まで、初心者の方にもわかりやすくご紹介します!
梅雨を少しでも快適に乗り切りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
✅食事で無理なく梅雨を乗り切りたいと感じている人
✅梅雨の時期になると体が重だるく感じる人
✅むくみやすく、体の水分バランスが気になる人
✅東洋医学や季節の養生に興味がある人
✅忙しくても手軽に体調管理をしたい人

昔から体が弱く年齢を重ねるにつれて、より様々な不調を感じるように。
自身で何とか体調を改善できないか?と、東洋医学やスパイス・ハーブなどを勉強。
セルフメディケーションカウンセラーの資格とスパイス&ハーブ検定資格を保有。
梅雨時期にとうもろこしをおすすめする理由
梅雨の体調不良ととうもろこしの関係
梅雨の時期になると、「なんだか体がだるい」「足がむくむ」「食欲がわかない」と感じることはありませんか?
これは、気温と湿度の高さが影響して、体に余分な水分(=湿気)がたまりやすくなるからです。
東洋医学では、このような不調のことを「湿邪(しつじゃ)」と呼びます。湿邪がたまると、体の巡りが悪くなり、だるさやむくみ、消化不良などの症状が出やすくなると言われています。
そんな梅雨の不調対策にぴったりの食材が「とうもろこし」。
とうもろこしには、余分な水分を外に出す「利尿作用」があり、体を内側からスッキリ整えてくれます。
さらに、とうもろこしは消化にやさしく、疲れた胃腸をサポートしてくれるのも嬉しいポイント。
梅雨のジメジメに負けない体づくりに、ぜひとうもろこしを取り入れてみてください。
とうもろこしの効能

薬膳の考え方では、食材にはそれぞれ「体を温める」「冷やす」「水分を出す」などの性質があります。
とうもろこしは「平性(へいせい)」という、体を冷やしすぎず温めすぎないバランスのよい性質を持っている食材です。
また、とうもろこしには「脾(ひ)」という消化器官を助ける働きがあり、梅雨に弱りがちな胃腸をやさしくサポートしてくれます。
さらに特筆すべきは、とうもろこしの“ひげ”部分。
実は「南蛮毛(なんばんげ)」と呼ばれ、漢方では利尿作用のある生薬として利用されているほどなんです。
つまり、とうもろこしは「実」も「ひげ」も丸ごと活用できる、梅雨時期にぴったりの“湿対策食材”。
日々の食事に取り入れることで、無理なく体調を整える薬膳的なアプローチが可能になります。
梅雨にうれしい!とうもろこしを使ったかんたんレシピ
梅雨時期はなんとなく気分も体も重く感じがち。そんなときこそ、旬のとうもろこしで食卓に彩りと元気をプラスしてみませんか?
ここでは、普段の食事にすぐ取り入れられる「かんたん・おいしい・体にうれしい」レシピをご紹介します。
とうもろこしの炊き込みごはん

【材料(2合分)】
- 米…2合
- とうもろこし…1本(または冷凍コーン・コーン缶100g)
- 塩…小さじ1/2
- 酒…大さじ1
【作り方】
- 米をといで炊飯器にセットし、通常通りの水加減にする
- 皮をむいて実を包丁でそいだとうもろこしを加える(芯も一緒に入れると風味UP)
- 塩と酒を入れて炊飯スタート
- 炊き上がったら芯を取り除き、全体を混ぜて完成!
冷凍コーンやコーン缶でもOK!その場合は、芯は入れずにそのまま炊いてください。
とうもろこしと豆腐のふんわりスープ
梅雨で胃腸が疲れ気味のときにもおすすめの、やさしい味わいのスープです。
【材料(2人分)】
- とうもろこし(または冷凍・缶詰)…100g
- 絹ごし豆腐…1/2丁
- 卵…1個
- 顆粒中華スープの素…小さじ2
- 水…400ml
- ごま油…少々
【作り方】
- 鍋に水と中華スープの素を入れて火にかける
- 沸騰したらとうもろこしと小さく切った豆腐を加える
- 再沸騰したら溶き卵を流し入れ、ふんわりかきたまにする
- 最後にごま油をたらして完成
食欲がなくてもスルッと食べやすく、朝ごはんや夜食にもぴったりの一品です。
冷凍コーンやコーン缶で手軽にとうもろこしを楽しもう
「とうもろこしは好きだけど、生のものは下ごしらえが大変…」「旬じゃないと手に入らないのでは?」
そんなふうに感じている方も多いかもしれません。でも実は、冷凍コーンやコーン缶を使えば、1年中いつでも手軽にとうもろこしの甘さと栄養を楽しめます!
ここでは、便利な市販品を使った活用術をご紹介します。
冷凍とうもろこしの魅力と使い方
冷凍とうもろこしは、実を加熱後すぐに急速冷凍してあるため、とうもろこし本来の甘みや栄養がしっかりキープされています。
使いたい分だけ取り出せるので、忙しい平日の調理にもぴったりです。
【こんなときにおすすめ】
- サラダの彩りにさっと加える
- スープや炒めものに凍ったままIN
- チーズと一緒にトーストや卵焼きに
時短&かんたんで、毎日の食卓が華やかになります。
コーン缶の魅力と使い方

コーン缶は常温で長期保存ができるのが魅力。ストックしておけば、思い立ったときにすぐ使えます。
缶を開けてすぐに食べられるので、料理が苦手な方や一人暮らしの方にもおすすめです。
【使い方のアイデア】
- ツナやマヨネーズと和えてコーンツナサラダ
- チャーハンに混ぜると甘みがアクセントに
- ハンバーグやミートソースに加えてコクUP
甘みがあるので、お子さまにも人気です。
汁気は軽く切ってから使うと、料理の仕上がりもきれいです。
冷凍・缶詰でも養生食材として活躍!
「生とうもろこしじゃないと効果がないのでは?」と思う方もいますが、冷凍や缶詰でも十分に養生の視点から役立ちます。
とうもろこしは、東洋医学で「脾(ひ)」を養い、余分な水分を出す食材とされています。冷凍や缶詰でもその性質は変わりません。
むしろ、保存がきくことで日常に取り入れやすくなる=続けやすいという大きなメリットも。
日々の料理に少しずつ取り入れることで、梅雨のだるさやむくみ対策として無理なく体を整えることができます。
むくみ対策やリラックスに◎ とうもろこし茶のすすめ
とうもろこしをもっと手軽に取り入れたい方には、「とうもろこし茶」もおすすめです。実はどちらも美容や養生にうれしい成分を含んだお茶なんです。
市販で手に入れやすく、ノンカフェインなので、夜寝る前のリラックスタイムにもぴったり。
ここでは、それぞれのお茶の特徴や効果、市販品の選び方をご紹介します。
とうもろこし茶とは?
とうもろこし茶は、とうもろこしの実や芯を焙煎して作られたお茶で、香ばしくほんのり甘い風味が特徴です。
韓国では「オクスス茶」として親しまれており、食事と一緒に飲まれることも多い飲み物です。
【主な成分と効果】
- カリウム:体内の余分な塩分を排出し、むくみ対策に◎
- 食物繊維:お腹の調子を整え、便通改善もサポート
- 鉄分・マグネシウム:女性にうれしいミネラル補給にも
市販では、ティーバッグタイプやペットボトルタイプがあり、手軽に取り入れられます。
市販でおすすめのとうもろこし茶
スーパーやドラッグストア、通販でも入手しやすいのでおすすめです。
無印良品のとうもろこし茶
水出しで手軽に作れるので暑い時期におすすめ!
ティーバックのお湯で入れるタイプもあるのでお好みに合わせて選べますよ!
大容量パックのとうもろこし茶
ネットでは大容量のものも売っているのでご家族がいたりたくさん飲む方はこちらもおすすめ!
ペットボトルタイプのとうもろこし茶
お茶作るのめんどくさい…というずぼらさんにはペットボトルタイプのお茶も出ているので気軽に取り入れられますよ!
どれもノンカフェインで体にやさしく、香ばしい風味で飲みやすいのが特徴。
お好みに合わせて取り入れてみてください。
日々の水分補給をとうもろこし茶に変えるだけでも、体の巡りを整え、梅雨の重だるさやむくみにアプローチできますよ。忙しい方やお料理が苦手な方にもぴったりの取り入れ方です。
まとめ
梅雨のだるさに「とうもろこし」を味方にしよう
湿気や気圧の変化で、なんとなく体が重い・やる気が出ない…そんな梅雨の不調には、とうもろこしが心強い味方。
カリウムや食物繊維など、体の巡りを整える栄養がたっぷり含まれ、東洋医学でも「湿をさばく食材」として知られています。
この記事のまとめ:
- とうもろこしは、体の余分な水分を排出してくれるカリウムが豊富
- 簡単レシピで、日々の食事に手軽にプラスできる
- 冷凍やコーン缶でもOK!常備しておけば便利
- とうもろこし茶やひげ茶で、内側から巡りをサポート
食事やお茶にとうもろこしを取り入れて、じめじめした季節を少しでも快適に。
“ゆるっと養生”、はじめてみませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
👇この記事を読んだ方におすすめの記事👇
【むくみ・だるさ】梅雨の不調に効く!はとむぎ茶の効果とは?
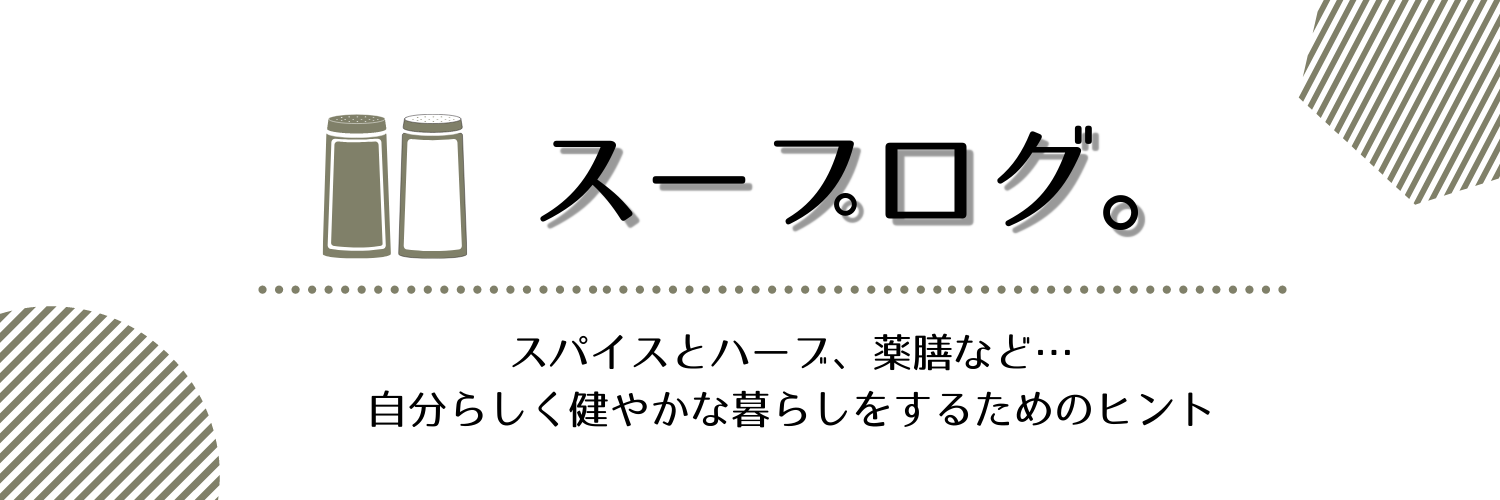
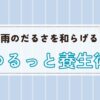


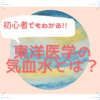
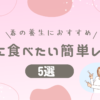
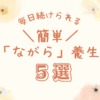

最近のコメント